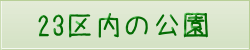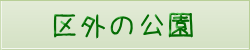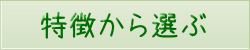水元公園の基本情報
以下では「水元公園」の基本情報についてご紹介します。
歴史
水元公園の開発の歴史は、1930年、旧都市計画法に基づき、かつて利根川の河川敷だった場所を「江戸川風致地区」に指定したのが始まり。その後、1940年に「水元大緑地」となり、1950年には「東京都江戸川水郷自然公園」として指定された。1957年からは東京都市計画計画に基づいた整備が進められ、約8年後の1965年4月、「水元公園」として開園した。
備考
面積は約93万平方メートル。小合溜(こあいだめ)と呼ばれる小さな河川から引いた大小の水路が園内を走り、都内随一の水郷景観を作りだしている。


利用案内
無料/無休
住所
東京都葛飾区水元公園3-2
アクセス
- JR常磐線「金町駅」
- 東京メトロ千代田線「金町駅」
- 京成バス「水元公園」
電話番号
03-3607-8321
公式サイト
水元公園の写真や動画
以下では「水元公園」について写真付きでご紹介します。



































「葛飾区金町運動場」。東端。東京都下水道局東金町ポンプ所に隣している。さらに東に進むと江戸川の河川敷に出る。川向こうは千葉県の松戸。



「水元公園・釣仙郷出入り口」。都道54号線に面した場所。

「ごんぱち池」。東側。都内唯一となるアサザの自生地。アサザは5~9月頃、水の上に黄色く可憐な花を咲かせる。

「旧水産試験場」。東側。戦後の重要なタンパク源として、コイ、フナの養殖や金魚の品種改良を行っていた場所。現在は東京都の天然記念物に指定されているオニバスの池や金魚の展示場がある。

「水辺散策池」。旧水産試験場の延長線上に細長く伸びる。水辺に群生するヨシや、オオヨシキリ(ウグイス科)、チョウトンボ、ヨシノボリ(ハゼ科)などを観察できる。


「花菖蒲園」(はなしょうぶえん)。全体的にひらがなの「し」の字型になっている公園の、ちょうど折れ曲がった所。明治神宮から譲り受けた古い江戸系品種を含め約100品種1万4千株の花菖蒲が植えられている。見頃は6月。



「水元大橋」。南北を結ぶ。中央入り口近くにある水色の橋で、当公園のシンボルにもなっている。

「円形広場」。中央出入り口から入ったところ。ひらがなの「し」の形をした公園の、ちょうど折り返し地点に当たる。

「涼亭」(りょうてい)。小合溜のほとりに建つ有料集会施設。休憩所も併設しているので軽飲食を楽しむことができる。

「ポプラ並木」。第一駐車場脇。高さ20メートルに達するポプラの並木が1.2キロ続く。

「メタセコイアの森」。北東。生きている化石として知られるメタセコイアが、約2千本植えられている。

「記念広場」。北東。小合溜を望む。

「森の散策路」。北東。記念広場から北に進んだところ。

「水生植物園」。北端。スイレンやヒシ、ガマ、ヨシなどたくさんの水生植物が植えられている。

「バードサンクチュアリ」。北端。3つの観察舎からサンクチュアリの中を覗くとサギやカワウなどを観察できる。

「北の菖蒲園」。公園のちょうど北端で、近くには水元グリーンプラザ(休憩所)がある。

「北から見た小合溜」。大きくS字状に蛇行しながら、公園の北縁に沿って広がる。

「水元公園・西出入口」。北西端。元々は神社林だった場所で、タブノキ、カヤ、ヤブツバキなどの常緑樹や、ケヤキ、エノキなどの落葉樹が生息している。

「閘門橋」(こうもんばし)。西出入口近く。1909年、古利根川と小合溜の水害防止のために建設された橋で、都内唯一のレンガ造りのアーチ橋。

「水元かわせみの里」。カワセミなどの野鳥や水生植物、魚の観察ができるほか動植物をわかりやすく展示している。また小合溜の水を浄化するという役割も持っている。

「ポプラ並木」。北西。高さ20メートルに達するポプラの並木が1.2キロ続く。

「バーベキュー広場」。北西。中央広場を見渡せる約1万平方メートルのエリア。利用料金は無料だが事前の予約が必要(03-5876-3434)。

「冒険広場」。北西。子供用の遊具あり。

「水元公園ドッグラン」。広さは約3,500平方メートル。小型犬専用エリアと、犬の大きさを問わないフリーエリアとに分かれている。利用は無料だが事前登録が必要。


「せせらぎ広場」。北区画の中央付近。中央広場を背景として人造のせせらぎが流れている。深さはくるぶしくらい。

「中央広場」。北区画の中央。なだらかな丘になっている。

「水元さくら堤」。園の南縁に沿って広がる。八代将軍・徳川吉宗時代の治水事業の名残。

「水元公園・中央出入口」。ひらがなの「し」のカーブした部分に当たる。まっすぐ進んだところが「円形広場」、および「小合溜」。