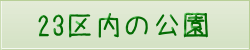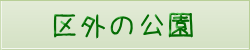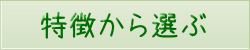飛鳥山公園の基本情報
以下では「飛鳥山公園」の基本情報についてご紹介します。
歴史
紀州徳川家の出自である八代将軍・吉宗は、この地に紀州ゆかりの王子神社があることを大いに喜び、元文2年(1737年)、飛鳥山を寄進した。その後、山の中に多くの桜が植えられ、江戸期における花見の名所となった地が、現在の当公園の原型と伝えられている。
備考
八代将軍吉宗が享保の改革の一環として、桜の名所地では禁止されていた「酒宴」や「仮装」を容認したため、江戸っ子たちは羽目を外して楽しんだという。また、時の町奉行・大岡越前が、近くに流れる音無川(石神井川の一部)の川岸に水茶屋を立てることを許可したことも手伝い、一躍桜の名所となった。


利用案内
無料/無休
住所
東京都北区王子1-1-3
アクセス
- JR京浜東北線「王子駅」
- 東京メトロ南北線「王子駅」
- 都電荒川線「王子駅前」
電話番号
03-3908-9275
公式サイト
飛鳥山公園の写真や動画
以下では「飛鳥山公園」について写真付きでご紹介します。



















「飛鳥山山頂」。JR京浜東北線「王子駅」中央口を出てすぐのところに公園入口があり、階段を登りきると飛鳥山の山頂北部に到達する。

「飛鳥山公園モノレール」。飛鳥山公園の公園入口から山頂間に設置した昇降設備。運行は10:00~16:00で乗車は無料。

「山頂モニュメント」。山頂北側。2006年に測量を行ったところ、標高は25.4メートルだった。これは東京で1番低いとされる港区の愛宕山(25.7メートル)よりも低い数字であるが、国土地理院には認められていない。

「飛鳥の小径」。ソメイヨシノやサトザクラなど約650本の桜のほか、約10種15,000株のつつじを鑑賞できる。また約350メートルに渡りアジサイが植えられている。

「桜賦の碑」。山頂の中ほど。1881年、勝海舟が建立。佐久間象山(1811~1864)の「桜賦」(さくらのふ)を元にした碑。桜賦とは、松代に幽閉された象山が、国の行く末を嘆き、その気持ちを国の花である「桜」に託して書いた文章。

「飛鳥山の碑」。山頂の中ほど。石は江戸城吹上庭園の滝見亭にあった紀州産の青石で、都の旧跡に指定されている。飛鳥山の由来を記す漢文は非常に難しく、江戸庶民の多くは「おそらく桜の枝を折るなと書いてあるのだろう」と思い込んでいたという。

「児童エリア」。山頂の南側。

「都電6080」。児童エリア内。作られたのは1949年で、1978年4月まで飛鳥山公園の脇にある荒川線を走っていた車両。

「D51-853」。児童エリア内。通称「デゴイチ」と呼ばれる蒸気機関車。1943年に製造された後、吹田、梅小路、姫路、長岡、酒田の機関区を渡り歩き、1972年に廃車となった。現役中の走行距離は194万キロに及ぶ。

「旧渋沢庭園・入口」。山頂南端。約2万8,000平方メートルの敷地に、日本館と西洋館をつないだ母屋の他にも色々な建物が建っていた。

「旧渋沢庭園」。住居は1945年の空襲で焼失したが、「晩香廬」(ばんこうろ)と「青淵文庫」(せいえんぶんこ)の2棟は、昔の面影をよくとどめている。庭園内には入れるが、建物の内部は毎週土曜日の午後のみ公開。


「晩香廬」(ばんこうろ)。渋沢栄一の喜寿を祝い、合資会社清水組(現:清水建設)の清水満之助が1917年に贈った小亭。晩香廬の名は、「バンガロー」に由来するといわれる。2005年には国指定重要文化財となった。

「青淵文庫」(せいえんぶんこ)。1925年、渋沢栄一80歳と子爵昇格を祝い、門下生の団体である「竜門社」によって寄贈された建物。2005年には国指定重要文化財となった。

「渋沢史料館」。渋沢庭園近く。日本の近代経済社会の基礎を築いた渋沢栄一(1840~1931)の全生涯にわたる資料を収蔵・展示している。

「北区飛鳥山博物館」。北区の自然・歴史・文化を紹介する博物館。

「紙の博物館」。世界有数の「紙」専門の博物館。

「多目的広場」。3つの博物館の前にあるスロープを降りきった所。能舞台をイメージした檜造りの野外ステージ「飛鳥舞台」もある。隣に走る道路は本郷通りで、北に直進すると王子神社がある。